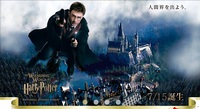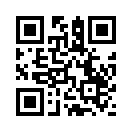「国勢調査 データで読み解く
ひとり暮らし世帯急増
4人家族モデル崩れる
2011年6月30日 日経新聞 5面」
長く日本の標準モデルだった「夫婦2人と子供2人」という家族像が
崩れつつあるようです。
国勢調査によると、1世帯あたりの人数は2.46人でおよそ半分の
世帯が一人暮らしか夫婦のみ、という現況のようです。
世帯人数は1960年の4.14人から減り続け、5年前の2.55人からさらに
減少しました。
背景にあるのは、一人暮らし世帯の急増です。
現在、ひとり暮らし世帯は1588万世帯で、子供のいる夫婦世帯
1458万世帯をはじめて上回ったとのことです。
特に、増加が顕著なのが65歳以上の一人暮らしで、高齢女性の
5人に一人、高齢男性の10人に一人が単身で暮らしている計算
になります。
男性の平均寿命が延びてきたとはいえ、女性平均で男性より
6年以上長生きする計算になります。
関連記事:「日本人の平均寿命、男性80歳で世界2位に」
核家族化、という言葉は今となっては古い言葉で、家族という
単位も形成できない単身世帯化が進んでいるようです。
家族の単位が少なくなると、リスクコントロールの面において
とても深刻な問題が発生します。
体調を崩したり、経済的に厳しい局面になったりしても、家族の
人数が多ければみんなで協力して乗り切ることもできますが、
一人、二人という世帯だと、そうしたトラブルを吸収する余地が
少なくなってしまいます。
例えば高齢夫婦のどちらかが病気や介護状態になれば、その負担は
相手に100%のしかかり、老老介護という状態になります。
そのまま愛情を持って相手を看取ることができても、今度は
残された自分は誰にも頼ることができなくなってしまいます。
そうした負担を経済的に補填しようと、生命保険などに加入する
方法もありますが、十分対応できる保障にしようとするには
高額な保険料が必要であり、一般的な家計においては「保険で
すべてまかなう」ということはほぼ不可能でしょう。
都会では、高齢単身者の孤独死問題も増加しています。
生涯未婚率も上がっているという現状もあります。
また、公的な保障である社会保障制度が負担しきれるかというと、
それも限界に来ています。
関連記事:「少子高齢化で社会保障の現役依存は限界」
先の読めない、混迷するこれからの時代のライフプランでは、
「家族のあり方」についても考える必要があるでしょう。
関連記事:

 浜松でファイナンシャルプランナー事務所を立ち上げました
浜松でファイナンシャルプランナー事務所を立ち上げました

 「ディズニー夏休み期間、子供半額キッズスマイルサマーキャンペーン」
「ディズニー夏休み期間、子供半額キッズスマイルサマーキャンペーン」
「【重要】税・社会保障改革で暮らしが変わります」
「節電が作る家族の絆」
「政局混迷、日本国債海外で信用力低下中」
「日本にも物価上昇が忍び寄る」
「高齢者雇用制度、県内は96%」
住宅ローンサポートセンター浜松
ファイナンシャルプランナー FP-dai

「30年後も笑顔」でいられることを目指す、浜松市のファイナンシャルプランナー

USJ値上げいつから?いくら?
仕事の満足度 社長89%、社員56%
サラリーマンでも簡単に副収入を得られる?
メディアに踊らされない家計になろう!
今年から代わる制度
増税対策、子供一人あたり1万円貰える?
仕事の満足度 社長89%、社員56%
サラリーマンでも簡単に副収入を得られる?
メディアに踊らされない家計になろう!
今年から代わる制度
増税対策、子供一人あたり1万円貰える?
Posted by 住宅ローンサポートセンター at
10:25│Comments(0)
│ニュース